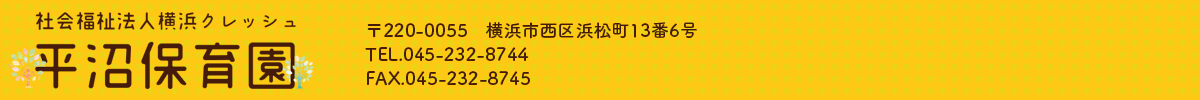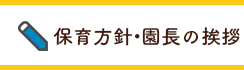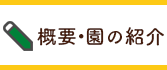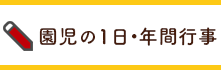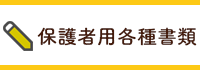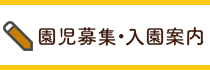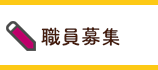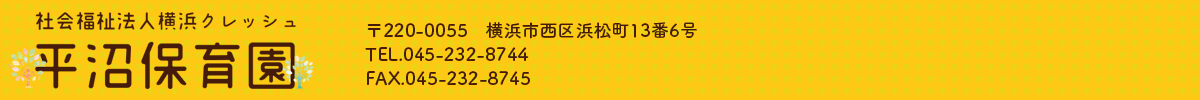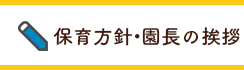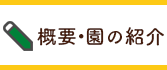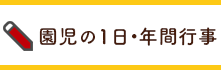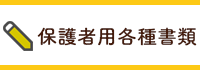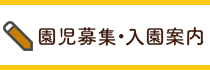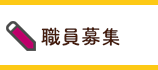|
項目
|
内容
|
評
価
|
評価の根拠・改善方法
|
|
A.B
C.D
|

子どもの発達・援助
|

(1)保育計画が保育の基本方針に基づき、さらに地域の意向等を考慮して作成されている。また、保護者の願いを反映している。
・指導計画の評価を定期的に行い、反省を生かし、結果に基づき指導計画を改定している。
・一人ひとりの子どもの発達状況に配慮した指導計画となっている。
|

B
|

保育課程は、保育の基本方針に基づき作成。
園目標は年度初めに前年度の子どもの姿を元に実態に合うように見直しをしている。
年間計画は、それに基に計画しているが、反省を生かし実態に沿った計画となるように努め月間計画へと繋げている。
|
|
(2)一人ひとりの子どもの発達状況、保育の実際について話し合うためのケース会議を定期的かつ必要に応じて開催している。
|
B
|
毎月末に個別の様子を記録し、一人ひとりにあった目標や配慮を考え、その後職員会議でケースについて話し合いを行い、全職員で情報の共有をし保育に反映している。
|
|
健康管理
|
(1)登園時や保育中の子どもの健康管理は、マニュアルなどがあり、子どもの一人ひとりの健康状況に応じて実施している。
|
B
|
登園時の視診、検温、保護者への聞き取り、連絡帳などで体調や怪我を把握し、職員間で報告し合い、対応できるようにしている。
|
|
(2)感染症への対応については、マニュアルがあり、発生に際してはその状況を保護者に連絡している。
|
B
|
感染症マニュアルを作成しておりそれに基づいて予防や発症に対応、発症した場合は保護者に掲示などで情報を速やかに伝え対応。感染症の情報を毎月のお便りなどで保護者に周知している。
|
|
(3)専門医から指示があった場合において、アレルギー疾患をもつ子どもの状況に応じて適切な対応を行っている。
|
A
|
アレルギー対応マニュアルに基づいて対応。担任、園長、調理員、保護者と毎月1回の話し合い(メニュー食材の確認)を行い、給食会議等で全職員への報告連携を密にし、児童票にも明記対応している。
|
|
(4)内科健診・歯科健診の結果について、職員や保護者に伝達し、それを保育に反映させている。
|
A
|
個々の結果を保護者に伝え、必要に応じて受診を勧めている。
|

|
|
食事
|
(1)食事を楽しむことができる工夫をしている。
・手作りおやつ、季節感のある旬の食材、喫食状況に基づいた食事内容、食育活動全般など工夫している。
|
A
|
食育計画の作成、手作りおやつは行事時にはその行事にふさわしいものを提供し(例:誕生会→ケーキなど)。年齢に応じプランターで季節の野菜を育て収穫し調理して食べる。
カレーやホットケーキなど、子どもが大好きで安全に調理できるメニューを選びクッキングも行っている。
|
|
(1)子どもの食生活を充実させるために、家庭と連携している。
|
A
|
給食サンプルを展示し、保護者に見てもらっている。参観日に給食を子どもと共に食べて、味付、形状喫食状況を見てもらい、意見を伺い調理担当者、栄養士に報告。また、調理担当者が給食時に子どもたちの喫食状況を把握することにより、充実した給食の提供を行えるようにしている。
|
|
(2)食物アレルギーは、個別に配慮し食事を提供している。
|
A
|
アレルギー対応マニュアルで対応している。給食やおやつ時は個別のトレーや容器に名前を書き、テーブルも別にし職員が一対一で関わる。
|
|
保育環境
|
(1)子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している。衛生面の配慮や不快なにおいへの配慮(手洗い場・トイレ)
|
B
|
玩具の消毒、室内の換気、湿度、温度などに配慮し、子どもたちが気持ちよく、また、感染症などが流行しないよう、衛生面にも心がけている。
チェックリストを作り、消毒の状況に落としがないかなど配慮している。
|
|
(2)生活の場に相応しい環境とする取り組みを行っている。
・子どもが不安になったりしたとき、いつでも応じられるように保育者が身近にいる。
・くつろいだり落ち着ける場所や眠くなった時に安心して眠ることができる空間が確保されている。
・食事のための空間の確保、季節ごとのインテリアの工夫、音楽や保育士の声の配慮など。
|
B
|
保育士が身近にいて、一人ひとりの子どもに寄り添い、気持ちの安定が図れるよう、職員間で共通理解をして対応している。
職員の声や室内の環境にも配慮し、子どもが安心感と信頼感をもって過ごせる場所となるように整備している。
|

|
|
保育内容
|
(1)子ども一人ひとりへの理解を深め、受容しようと努めている。
・子どもにわかりやすい温かな言葉づかいで話をしている。
・子どもの気持ちを受け止めてその都度対応している。
|
B
|
肯定感を持った言葉かけや自信をもてるような働きかけをしている。
個別の関わりを大切にした保育を行うようにしている。
|
|
(2)基本的な生活習慣や生理現象に間しては、一人ひとりの子どもの状況に応じて対応している。
|
B
|
一人ひとりの体調や体力を考慮し対応している。午睡に関しても、配慮の必要な子どもには、安心してできるように環境を整えている。
|
|
(3)環境の構成を意識した保育や過程を常に工夫している。
・子どもが自発的に活動できるように環境が整備されている。
・発達段階に応じた遊具、玩具が用意されている、素材・用具は自分で出して遊べる。好きな遊びのコーナーがある。
|
B
|
発達に応じた玩具や手作り玩具を用意している。好きな遊びが自発的に行えるように環境を整えている。また、異年齢での遊びも経験できるように配慮し、家庭的な雰囲気を心掛け、ごっこ遊びができるキッチン台を手作りして、コーナーを設置する等の工夫をしている。
|
|
(4)身近な自然や社会と関われるような取り組みがなされている。
|
B
|
自然物を使った遊びや製作、花や野菜の栽培活動、園外散歩等で社会事象や自然の命に関心が持てるようにしている。
|
|
(5)さまざまな表現活動が自由に体験できるように配慮されている。
|
B
|
年齢や表現の内容により、安全面から約束事やルール等を守り、その中で自由に表現ができる様にしている。廃材物を集め、自由に使い製作での表現活動も盛んにおこなわれている。
|
|
(6)遊びや生活を通して、人間関係が育つように配慮している。
|
B
|
子どもに固定観念を植え付けないよう職員も研修し、一層の配慮ができる様にしていきたい。
|
|
人権尊重
|
(1)子どもの人権に十分配慮するとともに、文化の違いを互いに尊重する心を育てるよう配慮している。
・子どもの権利擁護に関する研修に参加している。
|
B
|
子どもの人権を考慮し、文化・環境・生活習慣・考え方などの違いを認め、互いに尊重する心が育つように工夫している。
権利擁護に関する研修会等にも参加し職員自ら子どもたちに発する力を養っていきたい。
|
|
(2)性差への先入観による固定的な観念や役割分業意識を植え付けないよう配慮している。
|
B
|
子どもに固定観念を植え付けないよう職員も研修し、一層の配慮ができる様にしていきたい。
|

|
|
特別支援保育
|
(1)支援保育のために環境が整備され、保育の内容や方法に配慮ができている。
|
B
|
支援が必要とされる子においては、個別に支援記録を作成し保育を行っている。
|
|
(2)支援保育に携わる者は、支援を必要とする子どもを担当保育士は研修を受けている。
|
B
|
研修等で学んだ知識やその他の機関での情報収集に努め支援に活かしている。
|
|
(3)医療機関や専門機関から相談や助言を必要に応じて受けられる。
|
A
|
区役所の保健師、巡回発達相談(療育センター)など専門機関との連携をして助言を受け、保育に反映している。
|
|
(4)支援が必要な子どもの保護者に、適切な情報を伝えるための取り組みを行っている。
|
B
|
担任・主任が保護者との面談を設け、子どもの園での様子を伝え、家庭での様子を聞き取り、保護者の思いを尊重した上で子どもにとっての一番は何なのか?を一緒に考え、情報を提供し療育センターへの道を繋げている。
|
|
保護者会への支援
|
(1)医療機関、児童相談所の専門機関と連携をはかり保護者にとって必要な情報を提供している。
|
B
|
専門機関との連携が必要と判断した児においては、連携を図り保護者の方からの要望がない場合でも、頃合いを見つけて保護者に子どもの様子を伝えて専門機関との連携を勧めている
|
|
(2)一人ひとりの保護者と、日常的な情報交換に加え、個別面談などを行っている。
|
B
|
・送迎時に子どもの健康面や保育園での様子を伝えている。相談を受けた時には、内容により保護者からの要望があれば個別面談を行う。
・年に2回の個別面談の実施(全員)。
|
|
(3)家庭状況や保護者との情報交換の内容が必要に応じて記録されている。
|
B
|
保護者との情報交換(面談)などを行った時は、面談シートを作成し、情報の洩れのないように記録を保管。
|
|
(4)子どもの発達や育児について、懇談会等の話し合いの場に加えて保護者と共通理解を得るための懇談会を設ける。
|
B
|
保育参観の後や懇談会などで相談や意見が聞けるようにしている。保護者からの要望があればその都度対応している。
|
|
要保護児童への対応
|
(1)虐待を受けていると疑われる子どもの早期発見に努め、得られた情報が速やかに園長まで届く体制ができてる。
|
A
|
要支援の子どもに気づいた時は、職員会議等で情報の共有を図り、職員間で共通認識を図り対応している。
|
|
(2)虐待を受けていると疑われる子どもの保護者への対応について児童相談所等の関係期間に紹介、通告する体制が整っている。
|
A
|
組織としての通告の体制は整っている。区役所支援課との連携を密に取り、子どもに危険の無いように最善の注意を払い対応していく。
|

|
|
長時間保育の配慮
|
長時間にわたる保育のため環境が整備され、保育の内容や方法に配慮が見られる。
|
B
|
子どもが安心して過ごせるように配慮し、保育室の環境を整えている。健康面は細やかな気配りが必要なため、延長保育担当保育士や、保護者には担任からの伝達事項の漏れがないよう、連絡ノートを作成し、子どもの様子や連絡事項を伝えている。
|
|
説明責任
|
(1)理念や基本方針が利用者等に周知されている。
・情報提供(要覧・パンフレットなど)について伝える工夫をしている。
|
B
|
入園のしおりやホームページ、玄関、各クラスの出入り口付近など保育の目標、方針を掲示し、目標や目指す子ども像など周知している。
|
|
(2)利用者が意見を述べやすい体制が確保されている。
|
B
|
保護者の意見箱が玄関に設置されている。定期的に利用者アンケートを実施し、意見が述べられるようにしている。クラス懇談会においても職員が窓口となって相談や意見を聞き、保護者の要望に応えられるように、職員会議等で話し合いをして対応している。
|
|
安全対策・事故防止
|
(1)調理場、水回りなどの衛生管理はマニュアルに基づいて適切に実施されている。
|
A
|
衛生管理にはマニュアルに基づき、細心の注意を払って対応する。
|
|
(2)事故防止等のチェックリスト等があり、事故防止に向けた具体的な取り組みを行っている。
・施設の内外・設備の安全点検を計画的に行っている。
|
B
|
事故防止については、ヒヤリハット報告書に記入して、職員間で安全対策のため、情報を共有している。
・施設安全点検については、管理会社に依頼し、点検を行い安全を確認。
|
|
(3)不審者等の対応をする周到な配慮を行っている。
|
B
|
防犯マニュアルに沿って、年2回訓練を行っている。全クラス、避難時実際に対応できるか密に計画し、行動できるようにすることが課題。
|
|
(4)乳幼児の安全確保のため、家庭・地域社会・関係期間等と連携を図っている。
|
B
|
家庭とは、”eメッセージライト”での呼びかけなど連携がとれている。園外での安全確保においては、まだ一度も外への避難を行っていないので、来年度避難場所である西前小までいく避難訓練等を年間計画に入れることが課題。
・水害の場合、区役所からの避難指示場所は園児が歩いて行ける距離でないため、現実的に考えての避難場所の確保への取り組みを行わなくてはならない。水没地域ではないが、万が一の場合は園舎となりのビルの一室(事務所として法人で所有)が8階のため、そこへの避難も検討。
|

|
|
研修計画
|
(1)職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。
|
A
|
年度初めに各機関から発信されている研修を園長・主任とで検討し、キャリアアップに繋がるように計画したり、新人や各経験年数を考慮し、計画をたて実行。
|
|
(2)個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定され、計画に基づいて具体的な取り組みが行われている。
|
B
|
全職員が研修内容を周知し、計画に基づいて参加できるようにしている。
|
|
(3)定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。
|
B
|
研修後はレポートを作成し、ファイルを作り、皆で共有できるようにしている。
|
|
(4)資質の向上の取り組みを全市的に行っている。
|
A
|
保健・衛生・栄養等の研修は市・区で行われている研修等にも積極的に参加。
|
|
情報保護
|
(1)乳幼児や保護者に関する個人情報を適正に取り扱っている。
・利用者のプライバシー保護に関する規定マニュアルなどを整備している。
・遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みを行っている。
|
B
|
子どもの個人情報等は、守秘義務とプライバシー保護の観点で職員会議などで全職員に周知している。
個人情報に関しては所定の場所にファイルして保存している。法令に反した場合の取り組みはまだ完全ではなく、情報保護に関して徹底した取り組みをしていく。
マニュアルは今後作成。
|
|
苦情処理
|
(1)保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、迅速に対応している。
|
A
|
保護者より、相談や悩み等を受けた場合は速やかに職員間で協議し、保護者と話し合う機会を設けている。
直接保護者と話し合うことにより、保育園に対して理解してもらうことができている。
今後も迅速な対応をしていく。
|
|
(2)苦情解決の仕組みが確立され十分に周知、機能している。
|
B
|
重要説明事項や玄関などに苦情解決の仕組みが表示されており、今後も保護者の苦情や意見等に対して、迅速に対応が進められるようにしている。
|

|
|
地域との交流
|
(1)地域との関係が適切に確保されている。
|
A
|
立地条件に近隣が工場や単身者向けの住居なので、町内会には入っているが交流はおこなっていない。近隣では、ないが、所定の老人ホームとの交流はあり、月1の誕生日会には、手作りプレゼントを持参し、歌などを披露している。
|
|
(2)保育所が機能を地域に還元している。
|
B
|
親子支援活動として、地域の未就園児の親子を集めて、数園がグループとなり、親の育児相談を受けたり、子育てポイントなどアドバイスをして、園での保育の他に地域での活動にも積極的に参加している。現在、一時保育事業は行っていないが、今後行う方向で考えていきたい。
|
|
(3)ボランティアの受け入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。
|
B
|
ボランティアの話しがあれば、積極的に受け入れたいが、現在申し入れがない。
|
|
(4)地域の福祉向上のための取り組みを行っている。
|
C
|
取り組みをおこなっていないため、情報を把握して検討していきたい。
|
|
幼稚園・小学校との連携
|
(1)小学校・幼稚園との間で、行事などの交流する機会を設けており、職員間の研修などの連携体制が整備されている。
|
B
|
小学校とは定期的に交流会を行っている。小学校に出向き生徒や他園児との交流を行っている。また、就学に向けての支援を活用している。
その他、授業参観や運動会にも出むき、子どもたちがスムーズに進学できるように、道筋を作っている。
|